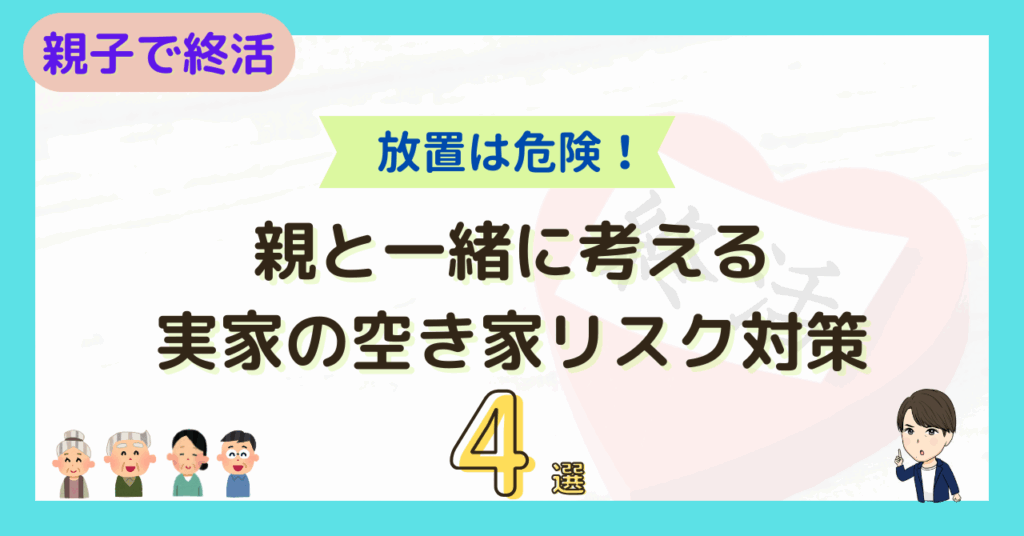
「実家が将来空き家になったらどうしよう…」
このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
私自身も静岡に高齢で単身住まいの母がおり、同じような不安を日々感じています。
実家は大切な思い出の場所である一方で、放置してしまうと予想以上に大きなリスクを生む可能性があります。
特に50代の私たち世代にとって、親御さんがまだ元気なうちに一緒に考えられるのは今この時期だからこそです。
今回は、不動産業界歴23年、終活の専門家としての経験を踏まえ、
「実家の空き家リスクを減らすための対策」を4つのステップでご紹介します。
なぜ実家の空き家対策が今重要なのか
実家には、かけがえのない思い出が詰まっています。
子どもの頃に遊んだ庭、家族団らんを過ごしたリビング、母親が作ってくれた料理の香りが漂うキッチン…。
これらすべてが、私たちの人生の一部となっています。
しかし同時に、不動産は「持っているだけで維持費がかかる資産」でもあります。
空き家になってしまうと、以下のような費用やリスクが発生し続けます。
継続的な費用負担
- 固定資産税:年間数万円から数十万円(地域・物件により異なる)
- 火災保険料:年間1〜3万円程度
- 修繕や清掃の費用:年間数万円から数十万円
- 庭の管理費用:草刈りや剪定で年間数万円
放置によるリスク
- 建物の老朽化進行:雨漏りや外壁の劣化が急速に進む
- 近隣への迷惑:雑草の繁茂、害虫の発生、景観の悪化
- 防犯上の問題:不法侵入や放火などの犯罪リスク
- 特定空き家指定:行政から強制的な改善命令や解体命令のリスク
これらの費用とリスクは、住む人がいなくても発生し続けてしまうため、早めの対策が不可欠です。
空き家リスクが生まれる現代特有の理由
空き家問題は、特別な家庭だけに起こるものではありません。
現代の多くのご家庭で共通する事情があります。
生活拠点の違い
親世代の家は郊外や地方にあるが、子世代は首都圏で仕事や子育ての生活基盤を築いているケースが大多数です。
そのため、実家を引き継いで住むという選択肢が現実的でない場合が多いです。
感情的な判断の先送り
親御さんが亡くなった直後は気持ちの整理がつかず、
「思い出の詰まった家を手放すなんて…」
という感情から、判断を先送りしてしまいがちです。
しかし、時間が経てば経つほど、建物の劣化は進み、対処が困難になります。
家族間の意見の相違
兄弟姉妹で「思い出を残したい派」と「現実的に処分したい派」に分かれ、
なかなか合意に達しないケースも珍しくありません。
コミュニケーション不足
最も重要なのは、親の本音を聞かないまま相続を迎えてしまうことです。
親御さんがどう考えているのかを知らずに、子世代だけで判断しようとすると、
方向性が定まりません。
こうして数年が経ち、気づいた頃には「荒れ果てた空き家」の状態。
資産価値が下がり、管理コストだけが膨らんでしまうという悪循環に陥ってしまいます。
実家の空き家リスクを減らす4つの具体的対策
対策1: 気軽な雑談から親の想いを聞く
「この家、将来どうしたい?」
といきなり切り出すと、多くの親御さんは構えてしまいます。
「まだ元気なのに縁起でもない」
と反発されることも少なくありません。
そこでおすすめなのが、「思い出話」を入口にすることです。
具体的な話の始め方
- 「この庭でよく遊んだね。お父さんが作ってくれたブランコ、まだあるね」
- 「ここで家族旅行の計画を立てたよね。あの時は楽しかったなあ」
- 「お母さんがこの台所で作ってくれた料理、今でも懐かしいよ」
- 「この部屋で宿題を見てもらったの、覚えてる?」
このような何気ない雑談から、自然と以下のような本音が見えてきます。
- 「この家がどれだけ大切か」
- 「どの場所に特に思い入れがあるか」
- 「将来どうしていきたいと考えているか」
会話はあくまで温かく、日常の延長線で進めることが大切です。
無理に結論を急がず、親御さんのペースに合わせましょう。
対策2: 制度や仕組みの情報収集をする
親御さんの想いを聞いたら、今度は子世代が現実的な情報を集めてみましょう。
正しい知識があることで、より建設的な話し合いができるようになります。
【活用できる主な制度】
①空き家バンク
- 自治体や地域団体が運営する仕組み
- 使われていない家を登録し、住みたい人や活用したい団体へ橋渡し
- 売却や賃貸のほか、地域の交流施設やシェアハウスなど多様な活用方法がある
②特定空き家制度
- 危険な状態や衛生上の問題がある空き家に対する行政指導
- 改善されない場合は強制的な措置も取られる
- 放置すればするほどリスクが高まることを理解しておく
③固定資産税の特例(住宅用地の減額措置)
- 家が建っている土地は固定資産税が最大6分の1に軽減
- 更地にすると軽減措置がなくなり、税負担が大幅に増える可能性
④自治体の補助金・相談窓口
- 解体費用の補助制度(自治体により異なる)
- 空き家の利活用に関する相談サービス
- リフォーム支援制度
「調べてみたら、こんな制度があるよ」と親御さんに伝えるだけで、話し合いの雰囲気が変わります。
情報収集は、親を安心させる「やさしいリード」なのです。
対策3: 将来の3つのシナリオを考える
「もしもの時」に備えて、ざっくりとシナリオを描いてみましょう。
選択肢を明確にすることで、家族の価値観や希望も見えてきます。
【シナリオ①】:残す
- 二拠点居住として活用(田舎暮らしを楽しむ)
- リフォームして快適な住環境に整える
- 思い出を残しつつ、新たな活用方法を見つける
- 家族の集合場所として維持する
【シナリオ②】:貸す
- 賃貸物件として貸し出し、家賃収入を得る
- 空き家バンクを通じて地域に活用してもらう
- 定期借家契約で一定期間のみ貸し出す
- シェアハウスや民泊として活用する
【シナリオ③】:手放す
- 売却して現金化し、相続税の納税資金に充てる
- 維持費負担から解放され、気持ちの整理をつける
- 寄附などで社会貢献する
- 解体して更地として売却する
大切なのは、親の想いを尊重しつつ、家族の生活スタイルに合った選択肢を考えることです。今すぐ決めなくても、「こういう可能性があるね」と整理しておくだけで十分意味があります。
対策4: 家族で「仮の結論」を共有する
最後に重要なのは、「今すぐ決めなくてもいい」という前提で、家族の仮の結論を共有しておくことです。
【共有しておくべき内容】
- 基本的な方向性(残す・貸す・手放すの大まかな方針)
- 決断の時期の目安(親の体調変化や施設入所のタイミングなど)
- 兄弟姉妹間での役割分担(誰が中心となって対応するか)
- 費用負担の考え方(維持費や処分費用をどう分担するか)
「とりあえず売却も視野に入れておこう」
「残す方向ならリフォーム費用も考えなきゃね」
といった「ゆるい合意」があるだけで、相続後の混乱はぐっと減ります。
結論を出すことよりも、「方向性を一度話してみる」ということが、何よりも家族を安心させるのです。
思い出を未来に残す工夫も大切
実家をどうするかという結論は家庭ごとに違っても、
写真や動画、声などを残しておけば「心のよりどころ」は決して失われません。
【記録に残しておきたいもの】
- 家族の思い出の場所の写真(リビング、キッチン、庭など)
- 親御さんが思い出を語っている動画
- 家の歴史や変遷の記録(いつ建てた、どんな改修をしたなど)
- 近所の方々とのエピソード
- 家族の集合写真やイベントの記録
特に、親御さんの声や表情、語り口調は、写真だけでは残せない貴重な記録です。
何気ない日常の会話から、人生観や価値観が伝わってきます。
まとめ:早めの対策が家族の安心と絆を深める
実家は「家族の思い出」であると同時に、「将来の課題」でもあります。
しかし、放置すれば負担になりますが、
少しずつ話し合いと準備を重ねれば、「未来につなぐ資産」へと変えていけます。
今回ご紹介した4つの対策は、その第一歩です。
- 雑談から親の想いを聞く – 自然な会話で本音を引き出す
- 制度や空き家バンクを調べて情報を集める – 正しい知識で建設的な話し合いを
- 3つのシナリオを描いてみる – 選択肢を明確にして家族の価値観を確認
- 仮の結論を家族で共有する – ゆるい合意で相続後の混乱を防ぐ
親御さんが元気で判断力がしっかりしているうちに準備をしておくことで、
将来の混乱や手続きの煩雑さを大幅に減らすことができます。
家族の思い出を形に残すという新しい選択肢
ここりんくす株式会社では、
実家を手放す前に、そこに詰まった家族の思い出や親御さんの人生を映像として残す
「リライフメモリーズ」というサービスを提供しています。
終活の専門家がインタビュー形式で親御さんの思い出や人生を丁寧に聞き取り、
映像クリエイターによる実家での撮影も交えながら、家族の記録を映像作品として残すことができます。
実家という「場所」は失っても、そこで育まれた「家族の物語」は永遠に残すことができます。
それは、どんな資産よりも価値ある「心の財産」となるはずです。
実家の将来について悩まれている方、親御さんとの大切な時間を形に残したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
今だからこそ残せる、かけがえのない家族の記憶を一緒に形にしてみませんか?
◆関連記事はこちら👇
