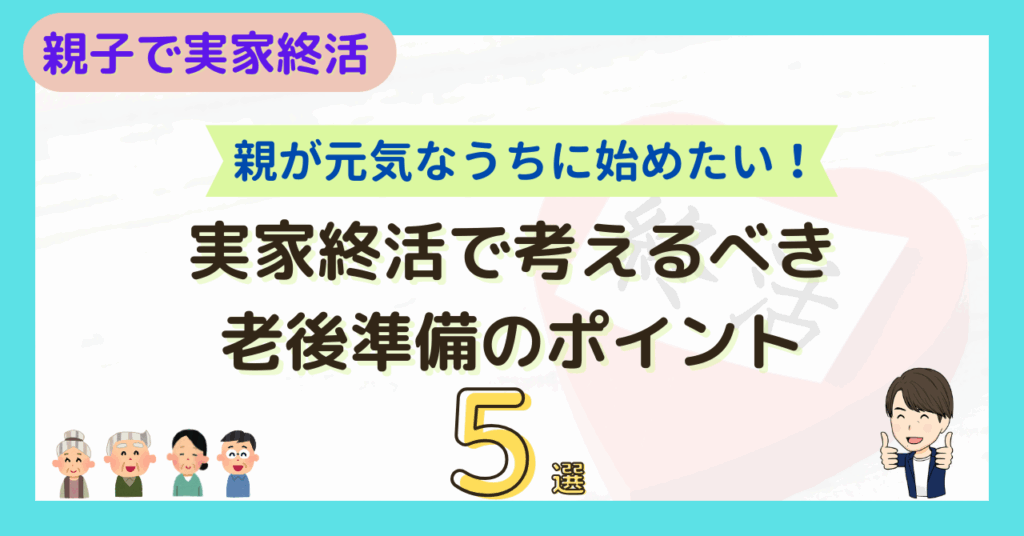
50代になると、子育てもひと段落し、
ふと「親のこれから」が気になり始める方が多いのではないでしょうか。
「介護になったらどうしよう」
「実家の維持は大丈夫だろうか
「老後資金は足りるのか」
こうした不安を抱えながらも、つい後回しにしてしまいがちです。
しかし、親御さんが元気で判断力のあるうちだからこそ、
一緒に考え準備できることがたくさんあります。
今回は、実家終活の観点から、親子で取り組むべき老後準備のポイントを5つご紹介します。
なぜ「元気なうち」の準備が重要なのか
長年、終活カウンセリングの現場に携わってきた経験から言えるのは、
多くのご家族が後悔する瞬間は「突然の出来事」に直面したときだということです。
「父が急に倒れて施設を慌てて探すことになった」
「認知症が進んでから本人の希望を聞けなくなった」
「実家を空き家にしてしまい管理に困っている」
こうした状況を避けるためには、次の3つが揃っているうちに準備を始めることが大切です。
1. 親の判断力がしっかりしている
ご本人の希望や価値観を直接聞き尊重できます。
2. 時間的余裕がある
焦らず、家族でじっくり話し合いながら選択肢を比較検討できます。
3. 感情的な負担が少ない
危機的状況でないからこそ冷静に前向きな会話ができます。
特に注意したいのは、「親の気持ち」「子の現実」「お金の制約」の3つが同時に絡み合う場面です。
親は「住み慣れた家を離れたくない」と願う一方で、
子世代は仕事や育児で実家に関わる余裕がなく
年金だけでは老後生活を支えきれない
こうした状況に陥る前に、早めに情報を整理しておくことが何より重要です。
親子で考えるべき老後準備の5つのポイント
ポイント1. 収入と支出の見える化(老後資金の確認)
老後のお金の不安を解消する第一歩は、
「入るお金」と「出ていくお金」を明確にすることです。
【収入の確認項目】
- 公的年金 : 年金定期便で受給額を確認
- 退職金・企業年金 : 受取時期と金額
- 資産収入 : 預貯金の利息、不動産賃料など
【支出の想定項目】
- 日常生活費 : 住まい、食費、光熱費
- 医療・介護費 : 年齢とともに増加傾向
- 住まいの維持費 : 固定資産税、修繕費
- 施設への入居費用 : 有料老人ホームなら入居金+月額20~30万円前後が目安
私がお勧めしているのは、親子で一緒に簡易的な「キャッシュフロー表」を作成することです。
今後10年、20年のお金の流れを可視化すれば
どのタイミングで資金が不足しそうか、どんな対策が必要かが見えてきます。
ポイント2. 住まいの選択肢の整理(実家をどうするか)
親御さんの住まいについては主に4つの選択肢があります。
① 現在の実家に住み続ける
メリット:住み慣れた環境で生活できる
デメリット:維持費、老朽化、安全性の課題
対策:バリアフリー改修、見守りサービスの導入
手すりの設置や段差解消などのバリアフリー改修は、
介護保険を活用すれば費用負担を軽減できます。
② 子世帯との同居
メリット:経済的効率が高い、日常的な見守りが可能
デメリット:生活スタイルの違いによるストレス
対策:事前に生活ルールを明確化
③ シニア向け住宅・施設への転居
メリット:医療・介護面での安心感
デメリット:費用負担が大きい
対策:早めに見学に行き、雰囲気や費用を把握
④ 実家を手放す・活用する
選択肢:売却、賃貸、空き家バンク登録
検討事項:建物の現状、売却価格、賃貸収益性、親の気持ち
ポイント3. 介護・医療費の備えの確認
公的介護保険があっても、自己負担はゼロにはなりません。
- 要介護度別の自己負担額の確認
要介護1で月1.7万円程度~ - 民間介護保険の必要性を検討
公的保険で不足する部分をカバー - 高額療養費制度の理解
医療費の月額上限の理解 - かかりつけ医や地域包括支援センターの情報整理
介護や医療にかかる費用は想像以上に大きいため、
早めに制度を理解し備えておくことが安心につながります。
ポイント4. 実家の活用方法の検討(空き家対策)
実家は感情的にも経済的にも大きな資産です。
以下の点を親子で確認しておきましょう。
確認項目チェックリスト
☐ 建物の築年数と修繕の必要性
☐ 固定資産税や維持費の年間コスト
☐ 売却した場合の概算価格(不動産会社3社に査定依頼)
☐ 賃貸に出した場合の収益性
☐ 空き家バンク登録の可能性
☐ 親御さんの気持ちと実際の住みやすさ
空き家リスク
- 老朽化による倒壊・事故
- 近隣トラブル
- 固定資産税の負担(特定空き家指定で最大6倍に)
- 防犯・防災リスク
実家の価値は築年数や立地によって大きく変わります。
早めに専門家に相談し現実的な選択肢を把握しておくことをお勧めします。
ポイント5. 親子での情報共有の仕組み作り
いざというときに困らないよう重要な情報を整理・共有しておきましょう。
- 銀行口座や保険証券の保管場所
- かかりつけ医や服薬情報
- 年金や各種契約の内容
- 緊急連絡先の一覧
- エンディングノートの活用
情報が整理されているだけでご家族の負担は大幅に軽減されます。
実家終活の進め方:実際の事例から学ぶ
【事例】首都圏在住50代長女Aさんのケース
<状況>
- 母親は地方の木造住宅で一人暮らし
- 母の希望:「この家に住み続けたい」
- 課題:冬の寒さ、建物の老朽化
<取り組んだこと>
- 母親と一緒に将来の生活費をシミュレーション
- 年金と預貯金では10年後に医療費・修繕費が不足すると判明
- 複数の選択肢を比較検討
- 近隣のサービス付き高齢者向け住宅を見学
<結果>
- 実家を売却し、その資金を老後生活資金に
- サービス付き高齢者向け住宅へ転居
- 母親:「実家を手放すのは寂しいけれど、安心して暮らせる場所ができて良かった」
<成功のポイント>
焦らず時間をかけて母親の気持ちに寄り添いながら、現実的な選択肢を一緒に考えたこと。
今すぐ始められる実家終活の第一歩
実家終活と聞くと重く感じるかもしれませんが、始めるのは意外とシンプルです。
すぐにできる5つのアクション
- 年金定期便の確認
親御さんと一緒に年金定期便を見ながら、受給額を確認する - 実家の現状把握
修繕履歴や維持費(固定資産税、光熱費など)を整理する - 施設の見学
休日に親子で介護施設やシニア向け住宅を見学する - 重要書類の確認
家族の連絡先や重要書類の保管場所を確認し、リスト化する - 定期的な対話
親御さんの希望や不安を聞く時間を定期的に作る
実践者の声:私自身の取り組み
私自身も地方に高齢で単身住まいの母がいます。
頻繁に帰省できないため、ZoomやLINEのビデオ通話を活用し、
定期的に母の不安や希望を聴く時間を作っています。
小さなことですが、継続することで親子の信頼関係が深まりいざというときもスムーズに対応できます。
遠方に住む親御さんをお持ちの方には特にオンラインツールの活用をお勧めします。
まとめ:親の想いと実家の記憶を残しながら前向きな準備を
実家終活で大切な5つのポイント(まとめ)
1.収入と支出の見える化:キャッシュフロー表で老後資金を把握
2.住まいの選択肢の整理:実家に住む・同居・施設・手放すの4択を検討
3.介護・医療費の備え:公的保険と自己負担を理解
4.実家の活用方法:空き家リスクを避ける対策
また、実家終活を進める上で忘れてはならないのが、「実家の思い出」をどう残すかという視点です。
どんな結論を選ぶにしても、親御さんが語る思い出や家族の歴史は、かけがえのない財産です。
私たちが提供する「リライフメモリーズ」は、
終活の専門家がインタビュー形式で親御さんの人生や思い出を丁寧に聞き取り、
映像クリエイターによる撮影も交えながら
家族の記憶を映像作品として残すサービスです。
【リライフメモリーズの特徴】
- エンディングノート作成サポート・終活相談付き
- 終活の専門家による丁寧なインタビュー
- プロの映像クリエイターによる撮影・編集
- 実家の風景や親の声、表情を記録
写真やモノを整理する前に、親の声や表情、実家の風景を映像に残しておくことで、
住まいやお金の話も自然に進めやすくなります。
実家を手放すことになったとしても、映像という形で思い出が残っていれば安心して前に進めます。
親御さんが元気な今だからこそ、家族の物語を未来へつなぐ準備を始めてみませんか。
◆関連記事はこちら👇
